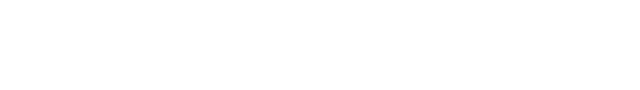【脂質異常症とは何か?正しく知ることが“将来の安心”につながります】|内分泌代謝専門医が解説|東京都中央区・日本橋
まずはじめに
「健康診断でコレステロールが高めだと言われたけれど、特に症状もないし、まだ大丈夫かな…」そう思われた方にこそ、ぜひ知っていただきたいことがあります。
脂質異常症とは、数字がすべてを決める病気ではありません。
“血液中の脂質が将来の血管にどんな影響を与えるのか”という視点が大切です。
脂質異常症の基本を専門医が解説
こんにちは。東京都中央区・日本橋で糖尿病と内分泌・代謝疾患の専門外来を担当している、玉寄皓大と申します。私はこれまで、内分泌代謝専門医として東大病院や聖路加国際病院などで糖尿病や脂質異常症の専門診療に携わってきました。本記事では、脂質異常症の基本をできるだけわかりやすくお伝えし、「知らないまま不安になる」ことを減らすお手伝いができればと願っています。
目次
- 脂質異常症とはどういう状態か
- どんな検査数値が異常とされるのか
- なぜ無症状でも対策が勧められるのか
- 数字だけで判断しないために──専門医の視点
- 正しい知識が、不安のない将来への第一歩です
1. 脂質異常症とはどういう状態か
脂質異常症とは、血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪など)のバランスが、医学的な基準から外れている状態を指します。「脂質」と一言でいっても、さまざまな種類があり、それぞれに役割があります。バランスが崩れると、血管の健康にじわじわと影響を及ぼす可能性があります。
2. どんな検査数値が異常とされるのか
下記の3つの項目が、健康診断などでよく目にする“脂質”の指標です。
| 指標 | 正常の目安 | 脂質異常とされる値 |
| LDLコレステロール(いわゆる悪玉) | 〜119mg/dl | 140mg/dl以上 |
| HDLコレステロール(いわゆる善玉) | 40mg/dl以上 | 40mg/dl未満 |
| 中性脂肪(トリグリセライド) | 〜149mg/dl | 150mg/dl以上 |
これらの数値は、単なる“高い・低い”で判断されるだけでなく、その方の年齢、体質(家族歴など)、他の病歴なども踏まえて解釈する必要があります。
3. なぜ無症状でも対策が勧められるのか
脂質異常症は、ほとんどの方に自覚症状がありません。しかし、数年・数十年かけて、血管の内側に少しずつ“変化”を起こすことがあるため、健康なうちに気をつけることが勧められます。例えるなら、これは「小さな積み重ねが大きな結果を生む」タイプの体のサインです。もちろんすべての方がすぐに治療が必要というわけではなく、生活習慣を少し整えるだけで十分なケースも多くあります。
4. 数字だけで判断しないために──内分泌代謝専門医の視点
脂質異常症と診断された方の中でも、
- すぐに薬が必要な方
- まずは食事・運動で様子を見るべき方
など、対応は人によって大きく異なります。その判断には、専門的な経験と、個別の背景(年齢、家族歴、他の病気の有無など)を読み解く力が求められます。
私自身、東大病院や聖路加国際病院などで、さまざまな患者さんの脂質異常症を診てきましたが、「同じ数値でも対応が異なる」ことは日常的にあります。
5. 正しい知識が、不安のない将来への第一歩です
「コレステロールが高めですね」と言われたとき、知識がないと「何か怖いことが起こるのでは…」と不安になってしまいがちです。でも、きちんと知れば、きちんと対応できます。脂質異常症は、「診断されたら終わり」ではなく、「早めに気づけたからこそ整えられる」ものです。
このシリーズでは、今後以下のようなトピックも順にお届けしていきます。
- 日常生活の中でできるコレステロール対策
- 薬が必要な場合と、そうでない場合の違い
- “家族性高コレステロール血症”という遺伝的な背景について
脂質異常症という“見えないサイン”を通じて、みなさまの将来の安心につながる選択のお手伝いができればと願っています。
著者紹介:
玉寄 皓大(たまよせ あきひろ)
- 日本内科学会認定 内科専門医
- 日本糖尿病学会認定 糖尿病専門医
- 日本内分泌学会認定 内分泌代謝科専門医
東大病院・聖路加国際病院で内分泌疾患・生活習慣病の診療に携わり、現在は東京都中央区日本橋のクリニックで糖尿病専門医・内分泌代謝専門医として日々の診療と情報発信に取り組んでいます。